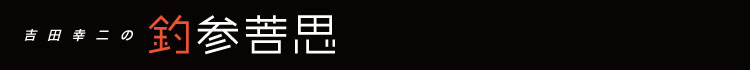
|
■霞ヶ浦の外来魚
このところ、国土交通省霞ヶ浦河川事務所主催の意見交換などに出席して、
ちょっと忙しい。釣りどころではない・・・なんてことはない。
この文章は否定形の否定だから肯定なんだよね。
つまり、『釣りどころ』である。ガッハッハッハッハー!
一生懸命に釣りをしているよ。ただ、何故かフナ釣りが多い。
ここに記したように、会議やらミーティング、会合などが多くて、
日長一日の釣りができないからなのだよ。
午前中二時間、夕方から三時間、昼過ぎに一時間、
なんて具合の釣りばっかりなので、
必然的にフナやタナゴなどの小物釣りが多くなる。
だから、「釣参菩思」の原稿も、
フナ釣り・・・なんてーわけには行かないので、
今回は読者のみんなにちょっと知識を持って貰おうと言うことで、
霞ヶ浦に移植された魚を紹介する。
移植された魚だから、外来種だ!
おいコラッ! そこで頭の中に?マークを浮かべている兄ちゃん、
外国から来た魚だけを外来種というのではないんだぞっ。
同じ日本の魚であっても、他所から移植された魚の全てを、
が・い・ら・い・ぎ・ょ(外来魚)と言うんだから、
しっかり頭の中に入れておきなさいよ。
実は、霞ヶ浦には下に列記した魚以外にも居るのだけれど、
主だった外来魚と言うことで頭に入れておいて欲しい。
霞ヶ浦外来魚
1、アオウオ:1943年に中華人民共和国より移入。
全長2メートルに達する超大物が棲息している。
が、30〜50cmの青年層を見かけないのはどうしてだろうか?
2、アカヒレタビラ:霞ヶ浦で最も多く見られるタナゴの仲間である。
産卵の時期になると、各ヒレの部位が赤くなることから
この名前がある。
●3、アメリカナマズ:ここ数年で爆発的に増えたのが、アメリカナマズである。
ルアーはもちろんのこと、ミミズや練り餌、
冷凍の魚、鶏のレバーなどを使っても釣れる。
食用として養殖業者が移入し養殖していたらしいが、
そこから脱走したものが現在では自然繁殖している。
4、オイカワ:霞ヶ浦本湖で釣れるのは非常に希で、
その多くは流入河川に見られる。
流入河川で釣れるオイカワは概ね13〜15cmほどで、
釣り味を十分に楽しめる。
●5、オオクチバス:日本に移入されたのは1925年。
この年、箱根の芦ノ湖に移植された。
芦ノ湖のバスのその後、1930年に長崎県や群馬県、兵庫県、
宮崎県、京都府など、各地に移植されている。
最初に見られたのは北浦の梶山周辺で、
その後霞ヶ浦の高浜入りで初めて採捕されている。
1998年頃から、販売経路の確立により乱獲されたため、
その生息数は大幅に減少している。
6、カネヒラ:日本に生息するタナゴの仲間で最大のもの。
本来は琵琶湖淀川水系以西にしか生息していなかったが、
他魚の放流に混入し、各地に広まった。
●7、カムルチー:1937年に朝鮮より移入されたが、その経路は不明である。
水生植物が豊富な頃は優占種となっていたが、
水質の悪化と水生植物の減少で減少の一途である。
現在、流入河川に僅かに見られる程度となっている。
8、カワムツ:本湖で釣れることは滅多になく、
その多くが流入河川域で釣れている。
これも元々は関東に棲息していなかったもので、
アユやフナ、コイなどの移入に混入したものである。
●9、ゲンゴロウブナ:1930年に雄103尾と雌54尾を琵琶湖より移入し、
県営の手野養魚場で蓄養。
翌年これらの親魚から30万粒を採卵し、これを土浦に放流。
その後、稚魚放流も合わせて放流は繰り返された。
新川や境川周辺にヘラブナ釣りが多いのは、その名残であろうか。
キンブナとギンブナをマブナと呼ぶのに対して、
このフナはビワコとも呼ばれていた。
10、コクレン:1943年に中華人民共和国より移入。アオウオ、ソウギョ、
ハクレンとこのコクレンを総称して、中国四大家魚と呼ぶ。
この年、四種の合計で一万五千尾が放流され、
いずれも中国の揚子江産である。
●11、コ イ :淡水の王と呼称されるコイであるが、その主だった理由は、
龍に変身すると言う中国の故事によるものであろう。
人間と千年以上ものつき合いのあるコイではあるが、
元々霞ヶ浦に棲息していたものとは別に、
新たに放流されたのは1868年頃という記録があるらしい。
●12、サンシャインバス:管理釣り場でストライパーが釣れるという情報から、
霞ヶ浦でこの魚の養殖が行われているという噂を耳にし、
八方手を尽くしたが養殖業者はまだ見つかっていない。
初めてサンシャインバスのことを知ったのが2000年で、
その後、捕獲された情報を聞かないので増えてはいないらしい。
13、スゴモロコ:琵琶湖淀川水系以西に分布してた魚であるが、
琵琶湖産コアユの放流に混入して移植されたようである。
14、ソウギョ:1943年に中華人民共和国より移入。(コクレンを参照)
15、タイリクバラタナゴ:1943年に中国四大家魚に混じって、
中華人民共和国より移入。
1950年には霞ヶ浦で繁殖しているのが見られた。
中国から来た赤いバラのような体色によって、
タイリクバラタナゴと呼ばれる。
16、タウナギ:1976年に霞ヶ浦で初めて採捕された。
ウナギという名前が付くがウナギ科ではなく、
タウナギ科という別種である。
田圃の畦に穴を空けるので嫌われ者であるが、
聞くところによると食用として移入したらしい。
小物釣りをしていると、空気を吸うため水面に顔を出す。
オレンジ色の顔がニョロッと飛び出すので大変に驚く。
17、チュウゴクオオタナゴ:2000年頃から新利根川周辺で釣れ始め、
2002年には麻生でも釣れるようになった。
真珠貝に入り込んでいたものが、
孵化して広まったと言う説もあるが。
18、ツチフキ:カマツカによく似ているが、顔が寸詰まりである。
近畿以西の各地に分布していたが、
1960年頃から霞ヶ浦で見られるようになった。
●19、ティラピア:1954年当時から、モザンビカ、ニロチカ、ホルノーラムなど、
数種が日本に移入された。が、10℃以下では成育しないために、
霞ヶ浦では定着しなかった。霞ヶ浦水産試験場では、
一時ティラピアを赤くする研究をしていた。
しかし、土浦の新川沿い下水処理場からの排水口では、
季節的な水温変化が少ないので、時折その姿を確認できるし、
釣れることもある。
20、ハクレン:1943年に中華人民共和国より移入。(コクレンを参照)
●21、ハ ス :琵琶湖や淀川のみに棲息していたハスが、
霞ヶ浦で一番最初に発見されたのが1962年である。
2000年まではたまに釣れる・・・程度であったが、
2001年に入ってからは驚くほどに釣れるようになった。
この増加に何が原因しているかは判らないが、
水の変化であることだけは確かである。
22、ビワヒガイ:1918年に250尾が桜川河口に放流された。
続いて、1948年にも202尾が放流された。その後爆発的に増え、
一時期は琵琶湖に逆販売するほどであったが、
1960年頃から減少する一方であった。
2001年頃から増加傾向にあり、
流入河川周辺では良く釣れるようになっている。
●23、ブルーギル:1960年に日本に移入されたが、霞ヶ浦に入った年は不明。
淡水真珠の稚貝養殖用に
琵琶湖から移入されたと言う噂であるが、定かではない。
●24、ペヘレイ:1966年に神奈川県淡水魚増殖試験場がアルゼンチンから移植し、
津久井湖に放流した。1985年に茨城県内水面水産試験場が移入し、
試験的に飼育した。その後、霞ヶ浦湖内で自然繁殖しているが、
どの様な経路で霞ヶ浦に入ったかは定かではない。
25、ホンモロコ:1936年に琵琶湖より75kg(およそ26000尾)が移入され放流された。
26、ワカサギ:それまではワカサギから採卵した卵を日本各地に移出していたが、
1969年初めて網走湖から移入。この年あたりから水環境が変わり、
霞ヶ浦の生態系は激変していく。
27、ワタカ :日本固有種で、琵琶湖や淀川に分布が限られていたが、
コアユの放流に混じり、全国に広がった。
霞ヶ浦では1960年に初めて採捕された。
参考文献:淡水魚(山と渓谷社)、淡水の魚と生物(学研)、霞ヶ浦の魚たち(筑波
書林)、霞ヶ浦の魚たち(霞ヶ浦情報センター)
●が付いているものは、過去にルアーで釣れた外来魚。
|
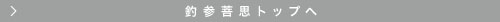
|